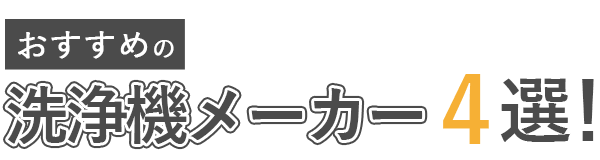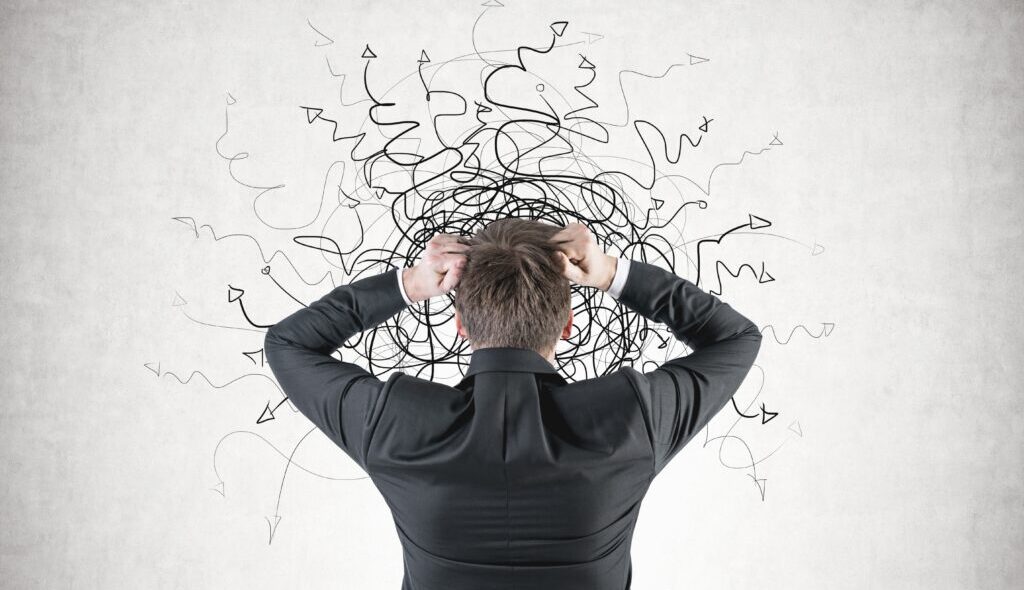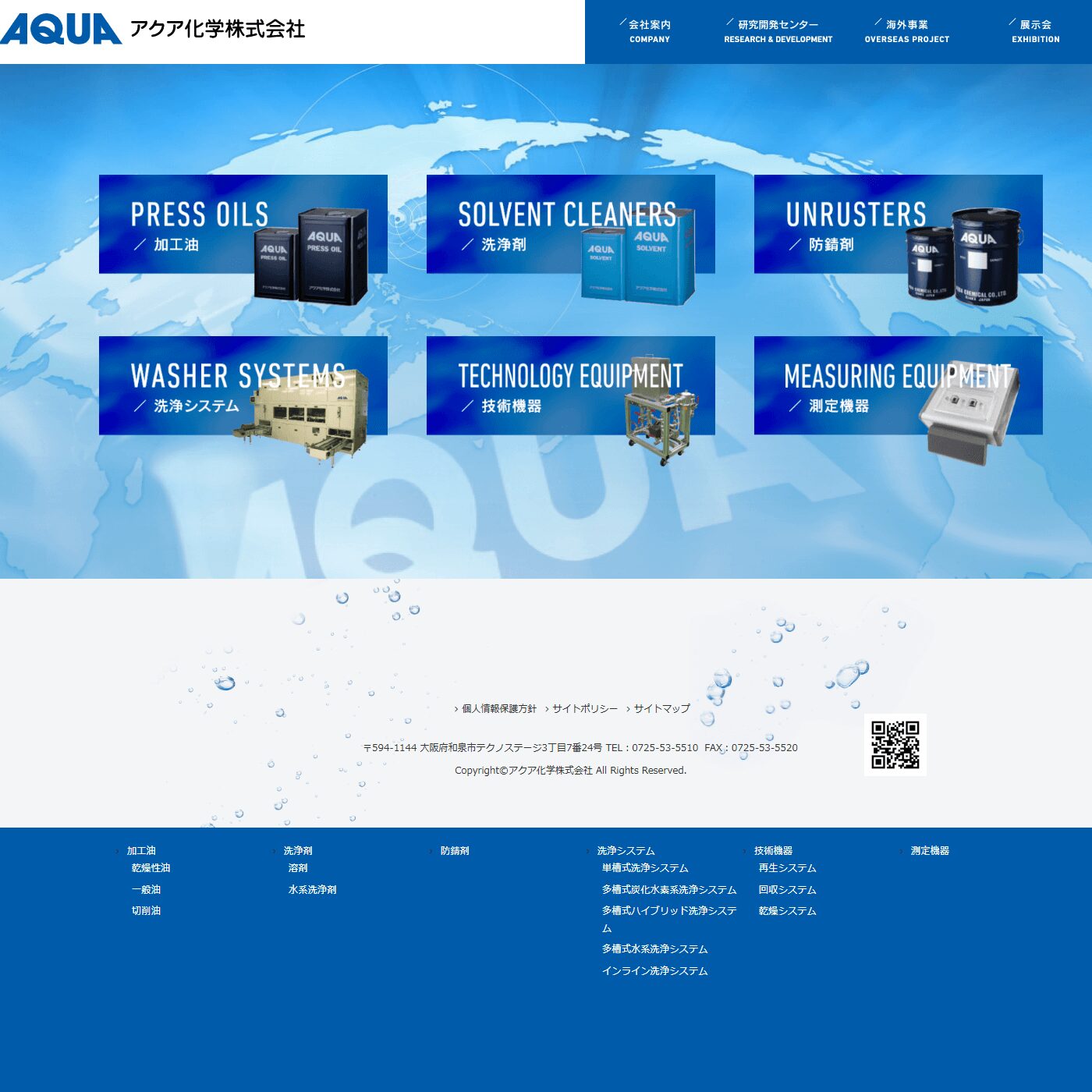製造現場において製品の品質を確保するには、洗浄工程が欠かせません。しかし「どこまで洗えば十分なのか」を判断するには、適切な評価方法が必要です。この記事では、業務用洗浄機の洗浄度を客観的に測る方法から、現場ですぐに活用できる簡易チェック法、さらに品質向上につなげるアプローチまでを解説します。
洗浄度の定量評価とは?
洗浄度の定量評価とは、洗浄後の製品表面に残る汚れや異物の量を数値として客観的に測定・評価する方法です。目視や感覚による主観的な判断ではなく、数値化することで誰が測定しても同じ結果が得られる品質管理が可能になります。この評価方法にはさまざまな手法があります。たとえば、顕微鏡による観察法では、洗浄後の製品を特殊な液体で超音波処理し、表面の微小な異物を剥がしてフィルターで集め、その数や大きさを計測します。
また重量測定法では、異物をフィルターに集めてその重さを量ることで汚れの残存量を判断します。とくに精密機器の製造現場では、分光光度法などの光学的手法も活用されています。紫外線や赤外線を使った分光測定では、製品から抽出した液体中の油分量を正確に測定できます。
また水滴の広がり具合を測る接触角測定法は、表面の油分残存状態を簡便に評価できる手法として知られています。国際的な評価基準としては、日本工業規格(JIS Z 8901)や国際電気標準会議規格(IEC 61340-5-1)などがあり、これらにもとづいた評価方法が広く採用されています。
たとえば、規定の布で製品表面を拭き取り、布に移った汚れの量や色の変化を測定する方法などが標準化されています。このように洗浄度の定量評価は、製造工程における品質保証の基盤となり、後工程でのトラブル防止に大きく貢献します。製品特性や要求される清浄度に応じて、適切な評価方法を選択することが重要です。
現場で即チェック!簡易評価ツールで油分残渣を可視化する方法
製造現場では高度な測定装置がなくても、洗浄状態を素早く確認できる方法があります。次の工程で接着や塗装を行う前に、部品表面の油分残りを確認することは品質維持に欠かせません。ここでは、日常的に活用できる簡易チェック法をご紹介します。まず注目したいのがブラックライト(紫外線ライト)による確認方法です。多くの工業用油剤には蛍光成分が含まれているため、暗所で紫外線を当てると残存油分が青白く光って見えます。
このツールは小型軽量で持ち運びが容易なため、大型部品の検査にも適しています。光の当たり方を変えながら表面をスキャンすることで、洗浄ムラも一目瞭然です。
とくに複雑な形状の部品や凹凸のある表面の検査に効果的で、洗い残しやすい隅や溝の確認にも威力を発揮します。次に表面張力検査用のダインペンも現場で重宝するツールです。
このペンで部品表面に線を引くと、油分が残っていると液体がはじかれて線が途切れます。反対に洗浄が十分であれば液体が均一に広がります。異なる表面張力値のペンを使い分けることで、洗浄度合いを段階的に評価することも可能です。
判定が視覚的でわかりやすいため、作業者の経験に左右されにくいのが特長です。水滴テストも手軽な方法のひとつです。洗浄面に水滴を落とし、その広がり具合を観察します。
脱脂が完全であれば水は薄く広がり、油分が残っていれば水玉のように丸まります。特別な道具が不要で即座に結果が得られるため、日常点検に最適です。
これらの簡易評価法は、精密な数値測定はできないものの、洗浄不良の早期発見や工程改善に役立ちます。定期的なチェックを習慣化することで、洗浄装置の不調も早期に察知できるでしょう。現場の実情に合わせて、これらの方法を組み合わせて活用するとよいでしょう。
不良ゼロへの第一歩!洗浄不良の見える化で品質トラブルを防ぐ
製造工程において、部品の洗浄は見過ごされがちですが、後工程の品質を大きく左右します。一見きれいに見える部品でも、微細な油分や汚れが残っていると、接着不良や塗装ムラなど深刻な問題を引き起こします。これらのトラブルを防ぐには、洗浄状態を「見える化」する取り組みが効果的です。重要なのは、洗浄不良と品質問題の因果関係を明確にすることです。たとえば、塗装のはがれが発生した製品を分析すると、表面に微量の油分が残っていたことが判明するケースがよくあります。
このような事例を社内で共有し、洗浄の重要性を認識させることが第一歩となります。洗浄状態を評価する方法としては、さきほど紹介した紫外線ライトやダインペンに加え、定期的なサンプリング検査も有効です。
とくに重要な製品は、一定割合を抜き取り、専門機関での分析に出すことで、より詳細なデータが得られます。収集したデータは単に記録するだけでなく、「洗浄品質マップ」として視覚化すると効果的です。
製品のどの部分に洗浄不良が集中しているかを図示することで、改善すべきポイントが明確になります。また、洗浄条件と不良率の相関を分析することも重要です。洗浄液の温度・濃度・時間などのパラメーターを変えながら最適条件を見つけ出し、その条件を標準化します。
さらに、洗浄装置の定期メンテナンスや洗浄液の適切な交換タイミングを設定することで、安定した洗浄品質を維持できます。現場作業者の意識向上も見逃せません。実際に不良が発生した製品と良品を比較展示し、洗浄不良がどのような品質問題につながるかを体感させることで、日常点検の精度が向上します。