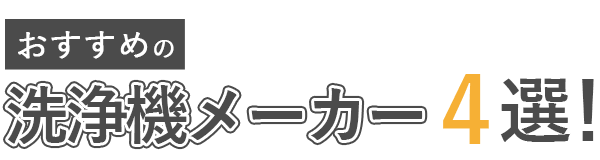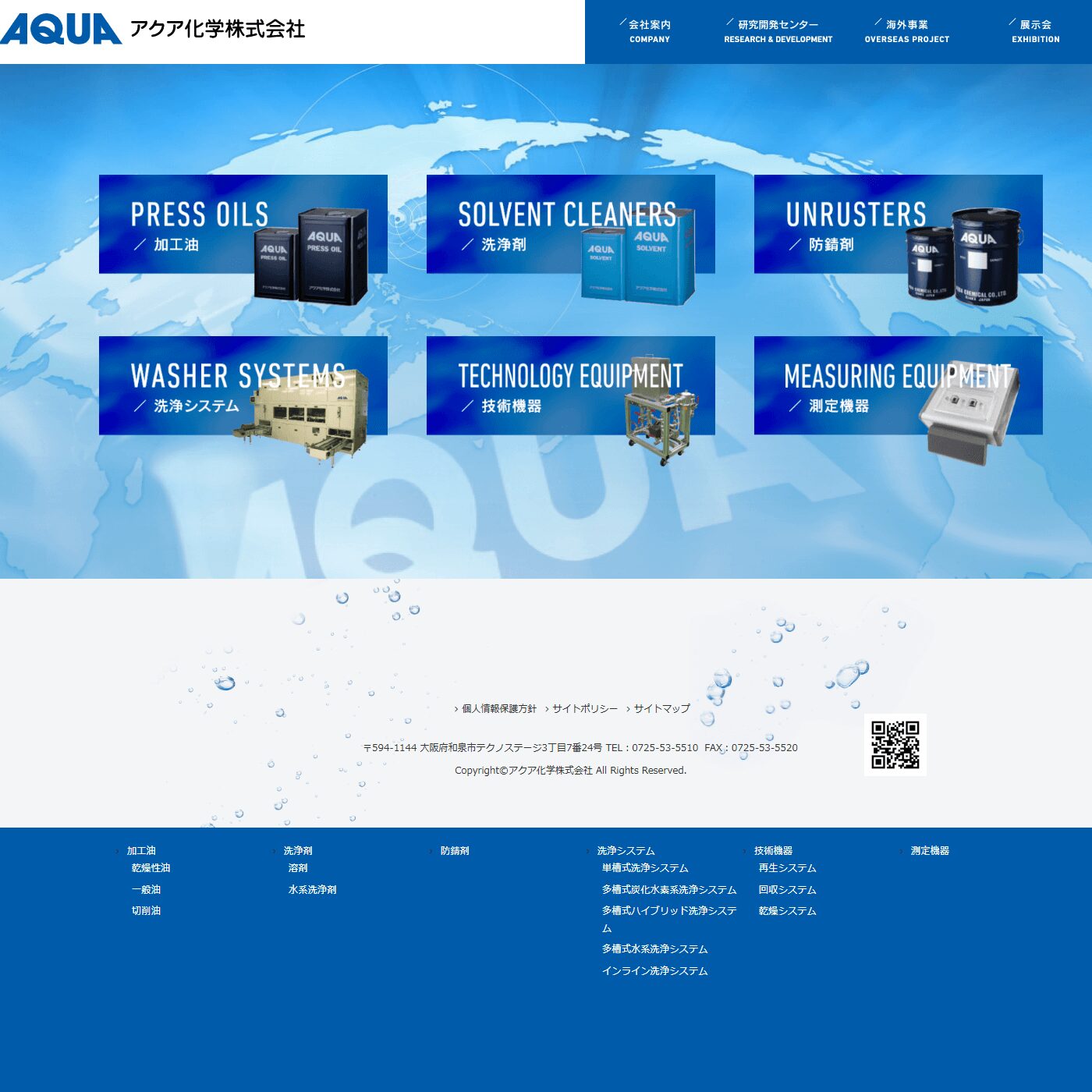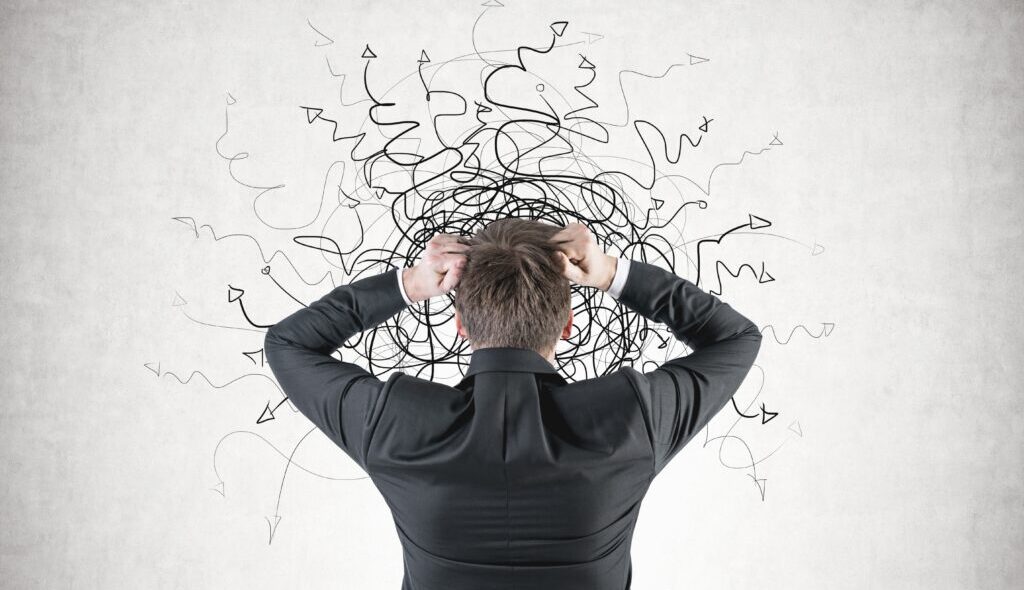洗浄剤にはさまざまなものがあり、汚れによって洗浄剤を使いわけることで効率的に汚れを落とすことができます。しかし効果が高いぶん、使用する際に注意が必要なものや法規制が定められているものがあるためルールを理解して使用する必要があります。今回は有機溶剤系洗浄剤について解説します。
有機溶剤系洗浄剤とは?
有機溶剤系洗浄剤の特徴や代表的な種類など、基本的な情報についてまずは解説します。有機溶剤系洗浄剤の特徴
有機溶剤系洗浄剤は油脂、脂溶性物質と結びつきやすい特徴があります。そのため油汚れや樹脂などを溶解でき、金属の表面や製造過程での付着物をスピーディーに取り除けます。製造業の分野で多く活用されており、自動車産業ではエンジン、トランスミッションなどの部品洗浄に用いられてきました。精密機器の現場では部品の洗浄、表面処理などに使われています。有機溶剤系洗浄剤は洗浄力が高いため、スピーディーかつ徹底的に汚れを洗浄できるメリットがあるのはもちろん、水を使用しないため、洗浄後に残留物が少なく、加工精度に影響を与えづらいというメリットもあります。
有機溶剤系洗浄剤の種類
溶剤によって特性が異なるため、用途に応じて溶剤を選ぶ必要があります。・クロロ系洗浄剤
洗浄力が高く金属の汚れや油汚れに効果を発揮します。
・アルコール系洗浄剤
速乾性があるため、電子部品、精密機械などの汚れに効果的です。
・ケトン系洗浄剤
塗料、接着剤などの溶解を得意としています。現場の製造過程での表面処理に役立ちます。
有機溶剤中毒予防規則(有機則)とは?
有機溶剤は活用することで効率的に作業を進められますが、呼吸する際や皮膚から吸収されるものがあるため、使用には注意が必要です。作業者の安全を守るために定められている規則について解説します。有機溶剤中毒予防規則とは
有機溶剤中毒予防規則は労働者の安全と健康を守る労働安全衛生法にもとづいた規則です。有機則と呼ぶことが多いです。第1種、2種、3種と有機溶剤は区分されており、毒性が最も強いものが第1種となります。規則の対象
工場や研究所で使用する場合は原則的に規則の対象です。使用量が基準を下回る場合は労働基準監督署に申し出を出せば、適用外の認定が受けられることを知っておくとよいでしょう。また、屋内の作業場では、壁4面のうち2面が開放されており、開放されている面積が4面の半分以上あれば規則の対象外です。許容消費量
第1種有機溶剤 W(g)=1/15 ×作業場の気積第2種有機溶剤 W(g)=2/5 ×作業場の気積
第3種有機溶剤 W(g)=3/2 ×作業場の気積
気積m3=作業場の縦m×横m×床上4m以下の高さm
(気積は最大150m3とし計算する)
有機則に該当する場合の企業側の義務と罰則リスク
有機溶剤は強力な洗浄力がありますが、有規則を守りながら使用しなければなりません。使用する際の義務やリスクについて解説します。企業側の義務
・主任者の専任屋内で有機溶剤を使用する際には作業主任者を選任する必要があります。主任者は2日間の講習を受け、合格する必要があります。
・換気装置の設置
有機溶剤に合わせた換気装置を設置する必要があり、毎月作業主任者が点検を行います。定期点検と結果を保存しなければいけない装置もあるので注意しましょう。
・作業環境の測定
1種、2種の有機溶剤を使う屋内作業場は、最低半年に1回のペースで作業環境測定士が作業環境を測定しなければなりません。社内に測定士がいれば社内で行えますが、いない場合は測定を外部業者に委託する必要があります。
・健康診断の実施義務
一般的な会社員の健康診断は1年に1回です。第1種、2種有機溶剤を常時取り扱う場合は、業務に就いた際、その後6か月ごとに有機溶剤健康診断が必要になります。使っている溶剤ごとに検査項目が追加され、健康診断が6か月に2回に増えるため、従業員の負担や企業のコストがかかるといえるでしょう。
企業側のリスク
・労基署の指導を受ける場合がある有機溶剤の使用には届け出は必要ありませんが、定期点検や健康診断を怠っていた事業者が労基署の指導を受けた事例があります。事業所の大きさに関わらず労基署から指導を受ける場合があるため、有機溶剤を使用するためには有規則をきちんと守らなければなりません。
・罰則を受ける場合がある
有規則を守らず、労基署の指導に応じない悪質なケースは3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科せられる場合があります。
・コストがかかる
有機溶剤を使用するためには換気装置の設置や点検、作業環境測定、健康診断、技能講習などにコストがかかります。また正しく使用しなかった場合は懲役や罰金を科せられるというリスクもあるのでコスト、リスク、ルールなどを正しく理解し運用しなければなりません。